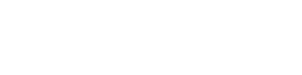記事詳細

高度急性期病院:院内に回復期リハビリテーション病棟を新設、回リハ患者の獲得と急性期病棟の在院日数の短縮
増益:稼働率20%UPと急性期1(旧7対1へ)の向上取り組み期間6か月当院は脳神経外科・整形外科に特化をした救急病院です。100床以下でありながら年間救急搬送件数が800件以上あり、重症度も高い高度急性期病院として地域の救急医療に関わっておりました。 しかしながら昨今のコロナ禍により、入院患者数の大幅な減少と、人件費をはじめ各種コストの大幅な増大と苦しい状況に直面しておりました。そこで当院での課題、地域の役割を再協議した結果、救急受け入れ後のリハ病院への転院が迅速に進まないこと、背景として地域の回復期病床が大きく不足していること、それに伴う平均在院日数の長期化が解決を要する事項としてあがりました。 それらを踏まえて院内での病棟を分化・増加し、「回復期リハビリテーション病棟」の申請を行うことで、救急患者の迅速なリハ提供と、救急病棟のベッドコントロール(次の救急を受け入れるためのベッド確保)を行いました。 結果、急性期病棟の平均在院日数は20日前後から15日前後になり急性期入院料1への向上も叶い、加えて病院全体の稼働率が20%あがることで、経営の安定化と地域の回復期病床の拡充に成功しております。